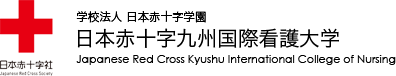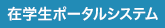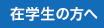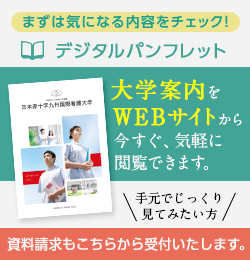『流れる星は生きている』
| 著者情報等 | (改版6版)、藤原てい著、中央公論新社、2002. |
| 寄稿者名 | 1年生 宮原 唯(2011年2月) |
| 本学所蔵 | http://opac.jrckicn.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=35385 |
著者の藤原ていは、1943年に夫である藤原寛人(作家の新田次郎)と満州に渡り、生まれて1ヶ月ほどの女の子を含む子供3人と、5人家族で満洲国の新京に暮らしていました。しかし、1945年8月9日のソ連の参戦後、夫とは別れ別れになり、幼い子供を日本に連れて帰る責任が著者の肩にかかってきました。日本に帰るために朝鮮半島を南下する道には、誰のものか分からない死体が転がっています。目の前で自決をしてしまう人もいます。いつソ連軍に狙われるかわからないという恐怖にも追い詰められます。乳飲み子を連れて旅をする困難は想像を絶するばかりで、「2人の子供と1人の子供、どちらが大事か」と下の子をあきらめるように勧める知人の言葉が著者の脳裏に浮かぶこともあります。それでも下の子だけ犠牲にすることなどできないと、「子供たちが途中で歩けなくなったら、子供3人を殺して、私も死のう」と、心に決める母・・・。しかし、母は子供の存在に助けられ、またもちろん子供は母に守られ、お互いの存在を頼りに、1日1日を生き延びたのでした。
私が最も深い印象を受けたのは、長男「正広」の言動です。食糧が十分に確保できなかった時には、自分のかじりかけの芋を「お母さん、お腹がすいて、おっぱいが出ないんでしょう」と、母に渡します。また、ひどく衰弱している次男「正彦」の様子を見て、自分も寒さと疲労に痛めつけられているのに、「正彦を死なせてはならない」と自分を鼓舞します。自分もまだ幼いといってもいい年齢なのに、長男としての責任を自覚し、弟や妹そして母を、やさしく思いやる男の子・・・そのけなげさに思わず涙がこぼれそうになります。
本書を読んで、もし自分が著者のように敗戦時に満洲国に住んでいたらどのような行動を取るだろうかと考えさせられました。私自身は、戦争があったことは知っていますが、戦争がどんなものなのか、人々がどんな状況下に置かれていたのかなどは、詳しく知りません。本書には、戦争の悲惨さだけではなく、そこに表れてくる極限状態の人間の行動や心理が鮮やかに描かれています。また、家族とはどんな存在なのだろうかと考える機会も与えてくれます。戦争の知らない世代の私たちが、是非読むべき一冊だと思います。