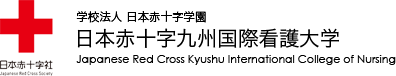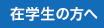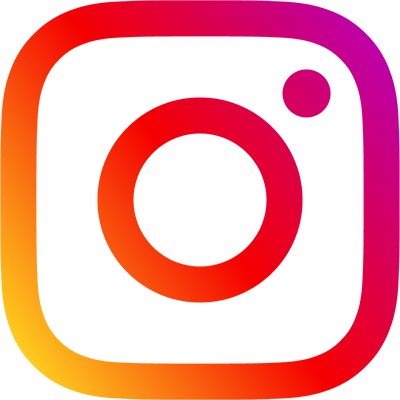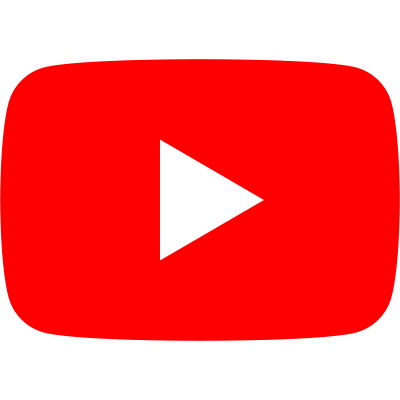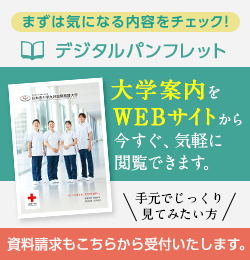第2回ランチョンミーティングを開催しました。今回は本学の成育看護学領域の助手である時枝夏子先生が、本年1月に笹川記念保健協力財団のホスピス緩和ケア研修の助成事業の一環としてアメリカのChildren’s National Medical Center in Washington, D.C.とSt. Jude Children’s Research Hospitalの2つの病院で行った研修の報告です。
死について公に語る機会がとても少ないと感じている日本では、医療者である私たちですら、子どもの死について語ること、また子ども“と”死について語り合うことはタブー視される傾向があります。しかしアメリカでは、子どもたちとしっかりと死について語り合っていることがとても印象的でした。
「子どもだから」、「どうせ分からないから」、と考えるのではなく、子どもを一人のヒトとして扱い、終末期にある子どもが最期まで子どもらしく生き抜くための支援や、患児やその家族が安心して在宅で終末期を過ごすことができるための支援が、医療者には求められているのだと思います。
時枝先生は最後に研修の中でであった3組の家族の事例について話をしてくださいました。処置の内容をしっかりと理解し、プレパレーションを通じてそのことを表現してくれた男の子、食事の方法を検討したことで笑顔を取り戻した子どもの母親を医療チームのパートナーとして扱った専門看護師、そして弟の死を受け入れていく過程でサヨナラのお手紙を書いたおにいちゃん。
小児緩和ケアという難しいテーマの講演でしたが、時枝先生の報告を聞いて、人の生きること、死ぬことに関わる私たち看護師は、まずは自分の生き方について考え、死生観を確立していく必要があるのではないかと考えました。


写真左:St. Jude Children’s Research Hospitalの創設者である、アメリカのコメディアン Danny Thomasの銅像
写真右:Children’s National Medical Center in Washingtonの入り口前