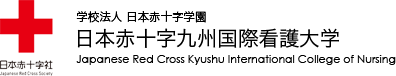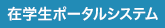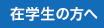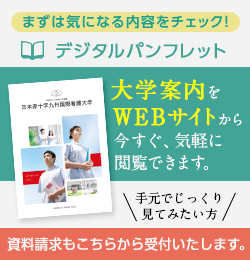『Man’s Search for Meaning』
| 著者情報等 | Viktor E. Frankl,Washington Square Press,1985. |
| 寄稿者名 | 1年生 森 明日香 (2015年2月) |
| 本学所蔵 | なし |
印象に残ったことが3つある。
一つは、フランクルの「運命に任せる」という言葉である。彼は、医師としてではなく普通の労働者として過酷な労働に従事させられていたのだが、発疹チフスが流行して医師が足りなくなったとき、重病者用の施設に行くように誘われる。行けば彼自身も死ぬ確率が高かった。彼を気に入っていた上役が行かなくて済むようにしてくれようとしたのだが、彼は、「どうせ死ぬなら意味のある死を」と考え、医師として自分の力を生かせる選択をした。そして、結果的に彼の命は失われなかった。ここで「自分の使命を全うしよう」と考えたことが、彼の運命を好転させたのかもしれないと私は思った。その後も、絶望するしかないと思われる状況でも、彼は、自暴自棄になることなく、運命を受け入れて一所懸命に行動し、運命は面白いくらいに次々と彼を良い方向へと導いた。未来のことは誰にもわからない、次の瞬間自分に何が起こるのかさえわからないということを、本書を読んで強く感じた。運命とは、一体何なのであろうか。
二つ目は、収容所の中の班長の中にも、被収容者に対して公平な態度を取る人がいたということである。殴る蹴るも普通の毎日を過ごす中では、殴られているほうだけでなく、殴っているほうも心が麻痺して、善悪の区別を感じなくなるのが普通だっただろう。それに、被収容者たちに優しい言葉をかけたり平等に接したりすれば、自分の仲間から非難される危険もあっただろう。しかし、そのような状況の中でも、周りに流されずに人間としてまっとうな行動を取り続けた人もいたのである。このことに私は強く心を打たれた。しかし、異様な環境に流されて残虐な行動を取っていた班長たちの心の奥底にも、良心があったのかもしれないとも思える。私自身がもし、「班長」の立場に立たされたとしたら、はたして良心を見失わずに行動できただろうか。
三つ目は、「愛は人が人として到達できる究極にして最高のものだ」というフランクルの言葉である。厳しい日々の中で、フランクルはときおり空を仰ぎ、妻と語っている気持ちになった。妻が答える声が聞こえ、微笑む顔が見えた。妻の生死すらわからないが、妻がこの世にいようがいまいが、その微笑みは太陽よりも明るく自分を照らしてくれた、と彼は書いている。また、「自分が苦しんで死ぬ代わりに、愛する人だけには苦しい死を免れさせたまえ」と、渾身の祈りを天に捧げる人もいたとも述べる。何も残されていなくても、心の奥底で愛する人の面影に思いを馳せれば至福の境地になれると、彼は言う。被収容者の心の最後の拠り所は、弾圧者への反抗心でも、理不尽な運命への呪詛でもなく、妻や家族や仕事など、愛するものを強く思う気持ちなのだった。このことに、私は深く感動した。
Man’s Search for Meaning の翻訳は出版されていないが、2014年後期の因京子教授担当のクラスの学生による本書の ”Experiences in a Concentration Camp” の章の翻訳が冊子になって、2015年春には図書館で閲覧できるようになる予定である。また、この部分はフランクルの著書の中で最も有名な『夜と霧』という邦題で新訳が出版され、大変読みやすくなっている。生、死、運命、愛、仕事など、人間にとって重要なことについて考えさせてくれるフランクルの著作を、看護学生は是非読んでほしい。