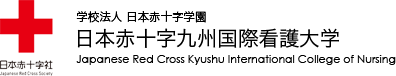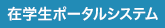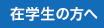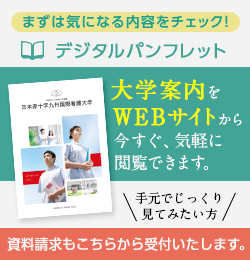『貧困の超克とツーリズム』
| 著者情報等 | 江口信清・藤巻政己編、明石書店、2010. |
| 寄稿者名 | 教授 鈴木 清史(2011年7月) |
| 本学所蔵 | http://opac.jrckicn.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=37104 |
時代がすすみ、大型航空機が定着すると、とくに先進国の人びとの余暇活動への渇望は観光を一大産業と変化させた。そして非日常の風物をたのしむ観光が「あたりまえ」になると、観光の消費者たち、つまり旅行者たちは、さらにべつの、異なる要素をもとめるようになった。たとえば、雄大な自然のなかをしんじられないほどの重さのバッグを背負い、数日間歩きまわるエコツアーが登場した。少数民族の村に短期間滞在し、食べ物や音楽をたのしんだりする文化体験ツアーももてはやされるようになった。これらは、金を支払う消費者がわざわざ大変な思い(苦労?)をするのを前提とする観光である。
一方、観光を提供する側からは別の見方もできる。観光は、既存の素材を活用する傾向にあり、初期投資のための資本は少なくてすむこともおおい。その割に現金収入を期待できたりもする。
たとえば、発展途上国では、青い海と白い砂浜、そしてその地の住民に固有の生活様式はおおきな観光資源である。何人にもおかされていない無垢な自然美は、先進国の雑踏をのがれたい人びとにとって「異国」情緒に溢れたおおいなる魅力とうつる(それが、自国ではかんがえられない安価でたのしむことができるなら、なおさらだろう)。その意味では、観光は、提供する側にとっても消費する側にとっても利害が一致しやすい経済活動なのである。
ここで紹介している文献におさめられた論文は、発展途上国や地域での観光現象をとりあげている。文化人類学者や地理学者が、自分で歩いて集めた資料をとおして、現地の人びとが観光という経済・社会現象にどのように立ちむかっているのをえがいている。将来国際看護に従事することを希望している人びとにとって、本書で登場する事例のおおくは、自分が現地に身をおいたとき、住民やかれらをとりまく社会にどのような眼差しをむけていけばいいのかをかんがえさせてくれるだろう。