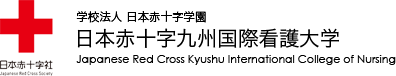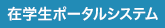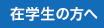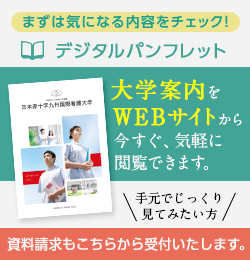『犠牲(サクリファイス):わが息子・脳死の11日』
| 著者情報等 | 柳田邦男著、文藝春秋、1995. |
| 寄稿者名 | 1年生 中野 誠也(2011年3月) |
| 本学所蔵 | http://opac.jrckicn.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=13096 |
洋二郎さんは、中学二年生の時に友人とチョークの投げ合いをしていて右目を直撃され、眼房内出血を起こし、出血が退くまでの11日間、入院治療をしました。その間に、強い失明恐怖に襲われ、この恐怖症にその後の些細な出来事が重なって、視線恐怖、対人恐怖、強迫思考を主訴とする神経症に陥ってしまいます。そして、苦しみ続けた挙句、自殺という道を選んでしまいました。著者とその家族は、洋二郎さんに回復の見込みがないことを告げられ、悩んだ末に、洋二郎さんが自己犠牲に思いを馳せていたことを考えて臓器提供を決意します。家族が、洋二郎さんと過ごした日々の記憶を辿り、彼の日記を読み返して、彼の苦しみを何とかして理解し、彼が真に苦しみから救われる道を考えようとしたその姿には、深く感動させられました。
私は、脳死についての著者の考えに注意を惹かれました。少なくとも本書が書かれた時点では、一旦脳死状態に陥ると回復することはないとされていました。人工的に延命は出来ても脳の機能が回復しなければ結局いつかは死んでしまう、従って、脳死は死と同じだと言う人もいます。これに対して著者は、脳死は「死そのもの」ではなく「死の前段階」であり、どの段階を死とするかは個人の選択に任せたほうがよいと言っています。「一般的には心停止を持って死とするが、どの段階での死を選択するかは生前の本人の意思による。特に、脳死を死とする場合は、本人の意思だけでなく近親者の同意を必要とする」と考えてはどうかと提案しています。この提案は、脳死となった段階で死と認められない家族の率直な気持を受容する一方、その家族が、時間の経過の中で気持ちを変え、臓器提供を受け入れる可能性もあることを考慮したものなのです。
私は脳死について深く考えたことはなかったのですが、漠然と、人の死は心停止によって全身の細胞の機能が停止してしまうことなのだろうと思っていました。脳死状態になり自発的生命活動を行えなくなっていても、全身の細胞が機能していれば、家族としては死とは認めにくいだろうと私は思います。脳死状態での死を受容するには、やはり、家族にも時間が必要なのではないでしょうか。著者が息子の死と向き合った、その実体験の中から出てきたこの提案には説得力があり、私は、この提案が一般化すればいいと思いました。
本書は普段は関係ないもののように思いがちな脳死のあり方について考えるきっかけを与えてくれ、また、家族、親子の絆についても考えさせてくれます。是非、手に取ってみてください。