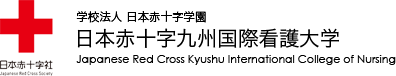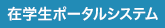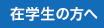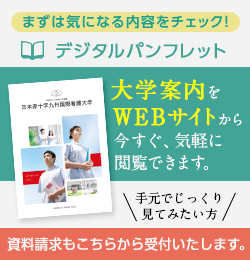『消えてしまいたい : ある女子大生の鬱病日記』
| 著者情報等 | 川上涼子著、文藝春秋、2003. |
| 寄稿者名 | 1年生 矢野 千帆(2013年2月) |
| 本学所蔵 | なし |
感情を言葉で表現することは、本当に難しい。それが、負の感情であるならば尚更だ。私は、「苦しい」とか「つらい」とか、定まった概念に押し込めることでしか、自分の感情を表現することはできない。しかし、それでは心の中で渦巻くわだかまりを完全に吐き出すことはできなかった。涼子さんは気持ちが沈む、やる気が出ない、死にたくなるなどの精神的な症状が現れるとき、「トコロテンがくる」と表現する。「トコロテン」が「天突き」から押し出されるように、ニュルニュルと襲ってくるのだという。自分一人の力ではどうしようもできない大きなものに飲み込まれそうになる感覚。私の心の中に鬱積したモヤモヤを、ぴたりと言い当てられた気がした。
また、彼女は台風が過ぎ去ったあとの、凪いだ海のように心が穏やかな日の胸の内を、「パステルカラーの、ピンク寄りのパープル」と表している。直接涼子さんの気持ちを体験したわけでも、感情を表す言葉が使われているわけでもないのに、こんなにも彼女の言葉が胸に響くのはなぜだろう。
涼子さんの文章には、一字一句が鋭い楔となって胸に打ち込まれていくような、力強さと重みがある。これほど著者の思いが伝わってくる作品を読むのは、私にとって初めてのことであった。それと同時に、その意味を深く考えさせられた。みなさんにも、この本のページをめくりながら、涼子さんと共に、悩み、喜び、そして考える時間を過ごしていただきたい。