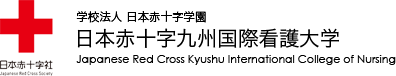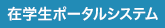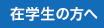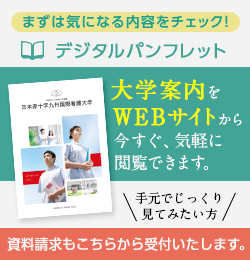『朽ちていった命:被曝治療83日間の記録』
| 著者情報等 | NHK「東海村臨海事故」取材班著、新潮社、 2006. |
| 寄稿者名 | 1年生 圓城寺 公美子(2011年9月) |
| 本学所蔵 | http://opac.jrckicn.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=36587 |
「東海村臨界事故」とは、1999年9月30日、東海村の燃料加工施設内で作業中にウラン溶液が臨界に達してしまい、至近距離で被爆した作業員が2名死亡した事故である。本書は、その一人、大内久さん(当時39)が亡くなるまでの83日を記録したものである。
読み終えた今、放射線の恐ろしさは尋常ではないということが、とにかく身に沁みた。この事故で核分裂反応を起こしたウランはわずか千分の1グラムだったそうだ。目にも見えない、極わずかな量の放射性物質の起こす反応でも、接触の仕方によっては、人を死に至らしめてしまう。私たちが今利用している原子力はそれほど危険なものなのだ。科学や医療が進歩したといっても、原子力は、私たち人間が完全に制御することが極めて難しい、あるいは、太刀打ちすることはほとんど不可能かもしれない、危険なものなのだ。ページを進めていくにつれ、この当然のことを改めて突きつけられた。非常に残念なのは、この事故が、原子力の利用には細心さの上にも細心さが必要ということを教えてくれたはずなのに、今回の東日本大震災で事故を起した福島原発には、この教訓が生かされていなかったのではないかと思われることである。「未曾有の天災だったから」では片付かない、人為的ミスも指摘され始めている。
本書には何枚かの写真が収められているが、その中に、因先生が涙を浮かべながら見せてくださった一枚の写真がある。その写真に、私も心を捉えられた。それは、被曝者が東大病院に搬送されてきて、まさに病院の建物に運び入れられようとしているところを撮影したものである。医療スタッフがストレッチャーを囲んでおり、その一番外側、最後尾に、カメラに背を向けて、一人の看護師がまっすぐに両手を広げている。患者を報道陣から、あるいは、全てのものから、護るように。その背中には、看護師の、静かな、強い覚悟が表れている。
本書の記述の中で、治療に従事した看護師の言葉には看護学生として特に興味を引き付けられた。その多くが彼女たちの葛藤を物語るものだった。「治る兆しすらないのにただひたすらに治療すること、それは患者にとって苦痛なのではないか」「私たちは無意味なことを続けているのではないか」・・・・。他人事とは思われなかった。これから、臨床実習、また、看護師として業務に携わる中で、このような葛藤に私たちもとらわれるだろう。本書の記述の中にはその葛藤に対する答はない。しかし、ヒントは、ある。覚悟を窺わせる看護師の背中に、そのヒントがあると私は思う。
将来の看護師として、そして原子力に恩恵を受けている国民の一人として、是非とも読んでいただきたい一冊である。