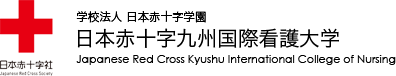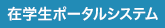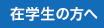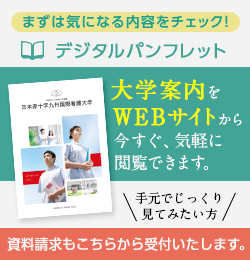『恍惚の人』
| 著者情報等 | 有吉佐和子著、新潮社、1972. |
| 寄稿者名 | 3年生 山崎 衣織(2012年11月) |
| 本学所蔵 | なし |
私はこの本をこれまでに何回か読み直しました。初めて読んだのは大学1年生の時です。次に、読み返したのは、ある先生から「親の介護ができるということは、それは親からのプレゼントである」という言葉を聞いたからです。始めはこの言葉の意味が理解できませんでした。しかし、読売新聞社が出している地下鉄のポスターに、書かれていた以下の言葉を読み、そして再びこの本を読み返しました。
「親が子を思う情はいつの世にも『永遠の片思い』であるという。
片思いに応えられる年齢になったとき、親はいない。
墓前にたたずめば人は誰もが『ばか野郎』となじってもらいたい親不孝な息子であり、娘であろう。」
親が自分の弱っている姿と不自由な動きを子供に見せ、介護をお願いすることは、恥ずかしく、またみじめさをも感じるものだと思います。だから、親が弱さをみせ、介護をさせてもらえるということが、最後の親孝行のチャンスであり、この機会こそが親からの渾身のプレゼントという意味だったのではないかと自分なりに解釈しました。
前述した、茂造が亡くなり、息子の言葉に昭子が涙する場面は、語弊があるかも知れませんが、介護する人の一つの達成感、息子の一言で報われた思いが現れているように思いました。
私が初めてこの本を読んだ大学1年生の時、そのときは介護者の負担の大きさと、辛さばかりに目がいっていましたが、今回、在宅看護実習を通して、家で療養する人とその家族を見て、そして、先生がおっしゃった言葉を考えながら読み返すと、一回目に読んだときとは違った視点から読み返すことができました。
本書は介護保険制度が整っていない40年前に書かれたものですが、書かれていることは今の介護の問題と変わらない部分が多くあります。40年という歳月の間に、科学はどんどん進歩しました。しかし、どんなに科学が進歩し、私たちの生活が便利になろうとも私たちは老いることから逃げることはできず、いつか私たちの親も、そして私たちも誰かの手を借りずには生きていけなくなります。
みなさんも人間に訪れる老いについて、特に自分の両親に訪れる老い、そして自分に降りかかる介護について考えたことがあるのではないでしょうか。誰もが直面する老いにどう向き合っていくのか、この本にはそのヒントが書かれています。ぜひ一度手に取ってみてください。