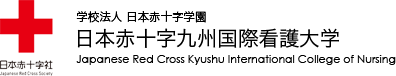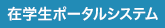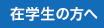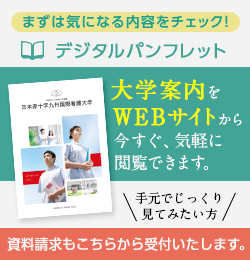『インパラの朝 : ユーラシア・アフリカ大陸684日』
| 著者情報等 | 中村安希著、集英社、2009. |
| 寄稿者名 | 1年生 唐田 佳奈(2012年12月) |
| 本学所蔵 | なし |
旅行記と聞いて想像する内容は、各国の文化や名所、郷土料理などについてがほとんどであった。しかし、この本はそういった内容はあまり記されてはいない。害虫が闊歩する中国の汚らしい電車や、イランの民家で食卓に上ったバラのジャムと家族との会話など一日の中のある一瞬についての記述がほとんどである。ケニアの草原で見た濡れたインパラの瞳や貧困に苦しむスラム街など、彼女のぶれない物差しを通して見る世界は、時に美しく時に残酷であった。
私が特に印象に残っているのは、パキスタン男子学生との会話の場面である。国境付近が雪で閉ざされ越境不可能になり、彼女はパキスタンに何週間か滞在を余儀なくされた。暇を持て余していた彼女は、宿に住み込みで働いていた学生とキッチンで談笑などをしていた。パキスタンはイスラム圏の国であり、シーア派やスンニ派といった宗教の派閥が人々を隔てる国でもあった。しかし、男子学生たちは異なった派閥同士にも関わらず深い友情で結ばれていた。当時日本で報道されていたような過激で排他的なイスラム教の影はなかった。彼らは純粋で優しかった。男子学生は彼女に、十年後には五人子供を作って待っている、再会の約束をした。まずは妻を探さないとね、と笑いながら。
旅行記は自分の視野を広げ、見聞を広めてくれる本である。『インパラの朝』はとりわけ、私たち日本人が抱きがちな価値観を打ち破るような内容だった。テレビで見るような事件で脚色された各国の印象とは違った面を、この本は教えてくれた。私たちが普段口にする「小さな声」。同じようにそれを零す個性豊かな人々が居る。『インパラの朝』はそんな人々の存在を教えてくれる素敵な出会いの書である。